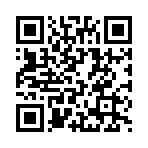2008年07月06日
ある歌集に寄せて
岐阜県中津川市にお住まいの大島登良夫さんから、第四歌集「恵麓後集 (けいろくこうしゅう) 」を頂いた。
大正二年生まれで九十五歳になられる大島さんは、私の所属している新アララギの同人であり、
歌壇の代表的存在である大島史洋さんの父君である。
以前、岐阜アララギの歌会で二度ばかりお会いしたことがあるが、小柄で優しい感じのする老人であった。
しかし、枯れたと見せかけて、その何処かに母性をくすぐるような色香を秘めた御仁のようでもであった。
大正二年生まれの丑年だと聞き、私の母と同年だったので、格別の親しさを抱いたのであったが、
大島さんも私に対して、わが子のような親しみを感じてくださったようであった。
■モロッコの美しいモザイクランプ。ムシャラビ(すかし模様)のランプも、ヤギの皮のランプも
どれも魅力的。山の家で履くバブーシュもモロッコ製。

さて、その恵麓後集であるが、
「あとがき」には恵那山の麓の小さな町に縁あって住み、朝夕仰ぎながら生きてきた故の歌集名であると記されている。
大島さんは、誰にとっても未知の分野の老いの日々を、淡々と生きていらっしゃる。
大上段に構えることも無く、そのひらめきや感慨を、短歌と言う定型に当て嵌めて昇華されている。
「平凡にして単調な歌のくり返しに過ぎないが致し方ない」と、謙遜されているが、
鋭い社会詠あり、自己内部への追及ありで、決して単調なくり返しなどではない。
病弱な自身の老体にも鞭を打ち、奥様の看取りもされ、
洗濯機の操作から始まり、ごみの分別や、味噌汁の作り方など、
やむを得ず覚えなければならないことが沢山あった。また、最愛の奥様も、旅立ってしまわれた。
生き残ることは、果たして幸福であろうか。
老いと孤独を凌ぐことは、悲しみであろうか。
語る人もない夜を、たった一人で耐えることが出来るだろうか。
大島さんなら耐えられる。押し寄せる諸々の悲しみを、明るい諦念に置き換えて、
短歌という型枠に閉じ込め、その楽しみに興じながら、淡々と生きてゆかれることだろう。
母性をくすぐるような色香を大切にされ、いつまでもお健やかにお過ごし下さいますように。
スポンサーリンク
Posted by 宣 at 17:46│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。